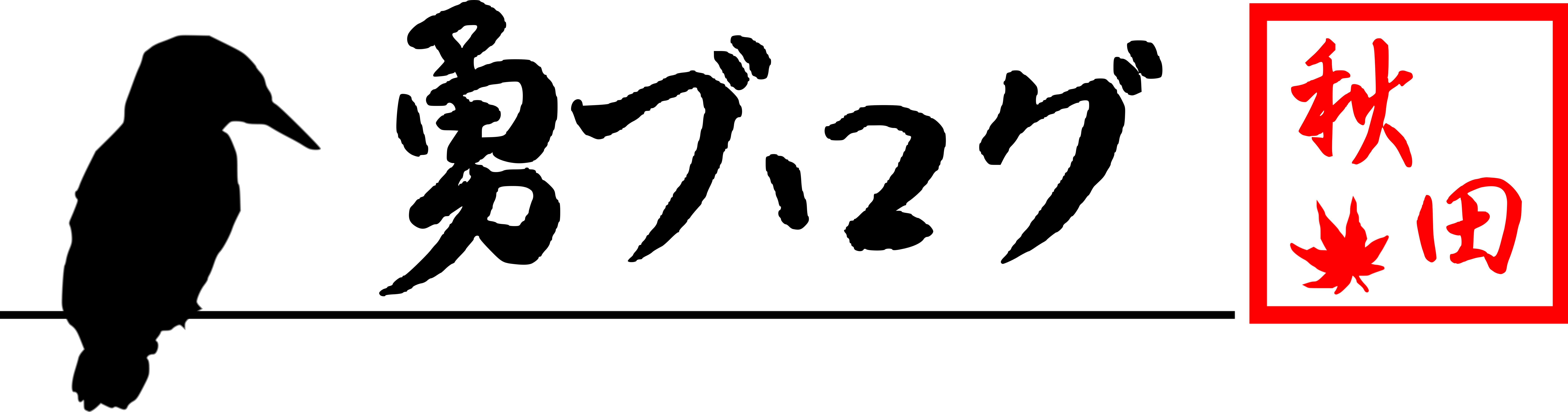こんにちわ,Isamuです。
EOS 7D Mark IIとEOS RPの2台体制で主に野鳥の撮影を続けていましたが、高画素機が欲しいと思うようになりました。
今回は、Sony高画素フルサイズミラーレスILCE-7RM3(α7R III)購入と、特徴や作例について紹介したいと思います。
目次
Sony高画素機の購入経緯
野鳥撮影を続けていく中で、もっと画質よく野鳥を撮影したい!と欲が出てきました。
これまで望遠端が400mmや600mmある超望遠ズームレンズを扱ってきて、撮影距離にも依りますがほとんどが写真現像時にはトリミングしていました。
センサーの画素の低いカメラではクロップした際にザラつきや低画素が目立ち、これはレンズだけの問題ではないと考えるようになりました。
このとき、Canonメーカに機材統一を図っており、EOS 7D MarkIIとEOS RPの2台体制で撮影を続けてきましたが、EOS R5のような高画素機ではないので、どうしても画質の面で歯がゆい思いをしていました。
EOS R5は価格も高価で、なかなか手が出しづらい現状にあります。
そこで、かつて扱った機材を思い返すと、Sony ILCE-6000やILCE-7M2は個人的にjpegで撮ったときの色味が好きで、さらにSonyなら決して安くはないもののセンサーの画素数の大きいカメラが私でも手が出せると調べたら分かりました。
Sony αRシリーズ・ILCE-7RM3
高画素機のRシリーズは高価ですが、Sony最強クラスのミラーレスカメラです。
秋田の過酷な環境でも存分に仕事できるポテンシャルを有しています。
広いダイナミックレンジ
ダイナミックレンジが広いと、日の出や夜景など明暗の差が激しいシーンにおいても綺麗に撮影できます。
日の出が遅く、日の入りが早い「秋田の冬」でも時間ギリギリ、いや最悪、夜明け前や、逆に日没後においてもしっかり仕事してくれると思います。
暗所での正確なAF
低輝度時(暗い時)でもAFが迷わなくなったらしいです。
低輝度時のAF速度は前機種「α7R II」比較で2倍程度に向上ということで、通年天候の悪い日が多い秋田ですが、そんな悪天候の中でも十分なパフォーマンスを発揮できると期待しています。
高精度なAF性能
動体追従性能や瞳AFの正確性など、AF性能が全体的に向上しています。
α1、α9などフラグシップ・ハイアマチュアモデルさながら、αシリーズは総じてAFの評判が良いので、動きの素早い野生動物の撮影などにおいて迷いなく合焦してくれる安心感のような心強さを感じさせてくれます。
秒10コマの高速連写性能
Canon EOS 7D Mark IIと同じ、秒10コマの高速連射性能があります。
連射性能も申し分なく、 野生動物の撮影において貴重なシャッターチャンスを逃さず撮影ができます。
秋田の四季・天気
先程からちらっと述べていますが、高画素機が欲しいことに加え、秋田の変わりやすい天候においても存分に使えるカメラとしてSonyミラーレスに目をつけたのが理由です。
そこで、秋田の四季や天気について少し触れておきます。
秋田は、四季を通じて春夏秋冬を感じることができる場所です。
春


夏

秋


冬

秋田は四季をはっきり感じられるメリットとは裏腹に、天候が変わりやすい・曇天が多いなど環境面でいえば不安定なところもあります。
お日様が出ていない中での撮影や、冬の吹雪、日が昇りきっていない夜明けなどISO感度が上げらざるをえない状況に出くわすことも多々あります。
このような悪天候・万華鏡のように変わる天候においても、撮影機会を逃さずに撮影に集中できる機材が必要だったのです。
機材の整理とILCE-7RM3のお迎え
ILCE-7RM3を購入するとなると予算が乏しく、既所有のカメラを合わせると4台になってしまいます。
カメラが多すぎますので、例のごとく、不要なカメラは売ってしまいましょう。
・Canon EOS RP
・RICOH GRIII
・Sony α7R III ←NEW!!
GRIIIはスナップ担当なので置いておいて、EFマウントに統一させてCanon機材で撮影してきましたが、やはりメーカーに囚われずに、自分の使い方にあった機材を使ったほうが効率の良いカメラライフを送ることができると判断しました。
Canonのフルサイズミラーレスは使用してみて使用感を把握できていたので、一旦EOS RPは売却し、貯金を切り崩してSonyフルサイズミラーレス ILCE-7RM3を購入することにしました。
私のILCE-7RM3の使い方
ILCE-7RM3(α7R III)は有効画素数が約4,240万画素のフルサイズミラーレス機です。
チルト式モニタを採用しており、手に収まるコンパクトボディなので扱いやすいです。

ミラーレスカメラについて私がいつも口酸っぱく言っていますが、撮影時に液晶モニタ場にはどのように撮れるのかその仕上がりが確認できるので、ミスショットを減らすことができます。
野鳥撮影において私はマニュアルモードをメインに使っています。
ISO感度はAutoで25600まで上限とし、F値とシャッタースピードを変化させ、とまりと飛びものの野鳥たちに柔軟に対応しています。
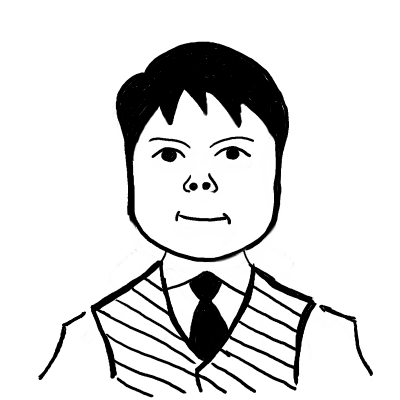 Isamu
Isamu

カメラ本体の重量は約657gであり、超望遠ズームレンズFE200-600mm Gレンズをつけても手持ちでの撮影は全然苦にならないです。
野鳥など撮影する方で、400mmや600mmなど100万超えの超望遠を購入できない方は、このレンズが本命になると思います。
三脚に据え付けてもいいですし、手持ちでふっ軽で撮影できます。

実写作例
ILCE-7RM3とFE200-600mm Gレンズを使って、いろんな野鳥を撮影してみました。
都市公園で見つけたカワラヒワです。
じっと立っていたら近くに降り立ってくれて、撮影距離は10m以内でした。

いつもの御池でカワセミを見つけました。
撮影距離は20mほどで背景をボカせました。

シャッタースピードを上げて、水面すれすれを飛行するカワセミも撮ってみました。

同じく距離20mの位置から街灯に止まったセグロセキレイを撮影しました。

渓流沿いで飛び立ったダイサギを撮影しました。

電線に留まるヤマセミを見つけました。
早朝での撮影でしたが、特に苦労することなく撮影できました。

川岸から突き出た木にカワガラスが留まっていた。
木のてっぺんや飛び出したものに留まる傾向がある野鳥は撮りやすくて好きです。

建物に止まっていたチュウヒです。
40m以上離れていましたが、FE200-600mmのテレ端600mmならそれなりの画質で野鳥をしっかり捉えられる。

雪降る渓流でカケスを見つけました。
カケスくんは単独、あるいは複数羽で行動しているようでした。

冬シーズンは派手な紅色が目立つ野鳥がいました。
ベニマシコの紅色の毛並みがキレイです。

まとめ
高画素機の導入で野鳥をはっきりくっきり撮影できるSony ILCE-7RM3を導入して機材整理を行いました。
Sony ILCE-7RMは現行機種のILCE-7RM4やILCE-7RM5に比べて型落ちですが、十分な性能を持っていると思います。
野鳥撮影を初めて数ヶ月が経とうしていますが、少しずつですが野鳥の観察種類も増えてきました。
「野鳥をなんとなく撮る」ことはできるようになってきたので、野鳥を撮るのは当たり前で「さらに質の高い写真を撮れる」ように動物撮影についてとことん追求していきたいと思います。
他にもカメラ機材の記事を執筆しているので、興味あればご覧になってください。
 Sony α7IIレンズキット(ILCE-7M2K)購入!初フルサイズ機
Sony α7IIレンズキット(ILCE-7M2K)購入!初フルサイズ機
 Sony ILCE-6000(α6000)購入!と使ってみた感想
Sony ILCE-6000(α6000)購入!と使ってみた感想
 Sony超望遠レンズ・FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS(SEL200600G)
Sony超望遠レンズ・FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS(SEL200600G)
 風景・スナップ撮影用コンデジ RICOH「GRIII」
風景・スナップ撮影用コンデジ RICOH「GRIII」
 Canonフルサイズミラーレス「EOS RP」導入と使用感
Canonフルサイズミラーレス「EOS RP」導入と使用感
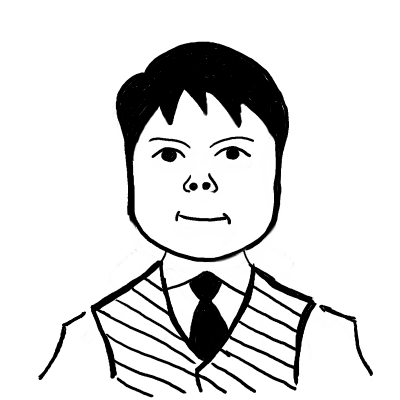 Isamu
Isamu
7DMarkII Canon EF70-200mm EF100-400mm EF400mmf4 EOSR7 EOS RP FE200-600mm FEマウント ILCE-7RM3 ILCE-9 Instagram K-S2 PENTAX Sigma150-600mm SKYLUM SNS戦略 Sony TAMRON α7RIII ズームレンズ ツキノワグマ ドットサイト ネイチャー フィーチャー フォトコン フォトコンテスト プリント ミラーレス ミラーレス一眼 レビュー 一眼レフ 仁別 写真 写真展 写真現像 動物 望遠レンズ 照準器 秋田 自然風景 超望遠レンズ 野生鳥獣 野鳥 風景