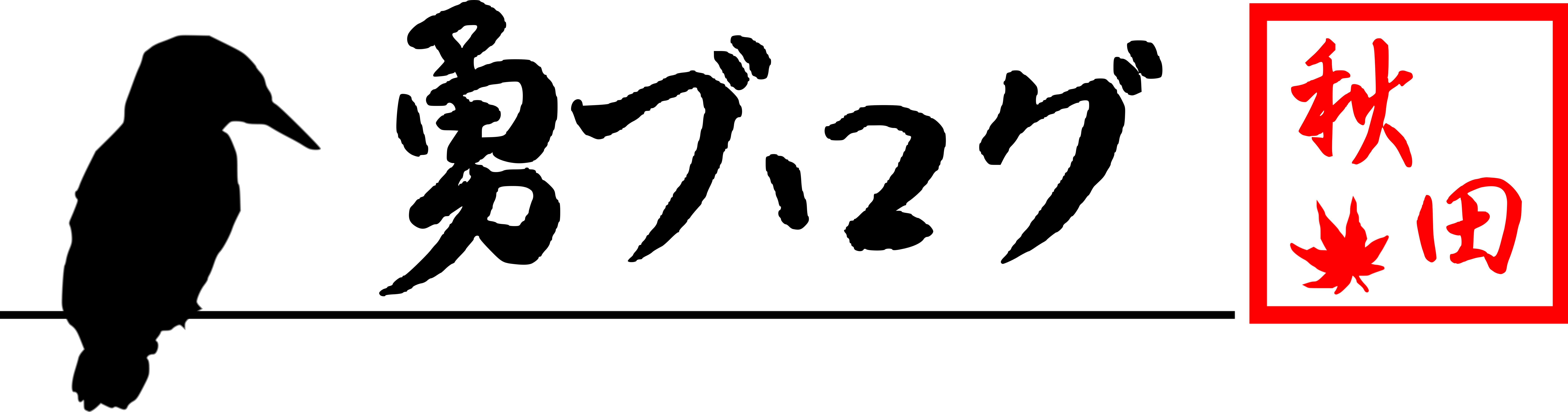こんにちわ,Isamuです。
野鳥を撮影する中で、飛びもの(野鳥の飛翔)写真を撮ってみたいと思い始めたころ、照準器を使っている人が多いことに気づきました。
照準器は別名、ドットサイトなどとも呼ばれ、ここでは照準器と統一して記述します。
照準器というのは、ライフルなどの上に取り付けられており、対象物に狙いを定める際に覗き込むアレのことです。
この記事では、高価な照準器ではなく、安価なモデルでとりあえず照準器使ってみたい人向けの内容になります。
目次
ANS Optical JH400
照準器はフロントサイト(液晶の窓)にレティクル(赤や緑で目標にあわせるための目印)が表示されて、それを標的にあわせます。
主に、銃に取り付けて狩猟で使ったり、カメラに取り付けて写真を撮ったりする事が多いようです。
また、照準器には電源が必要で、下記モデルだとCR2032電池(3V)1個が必要です。
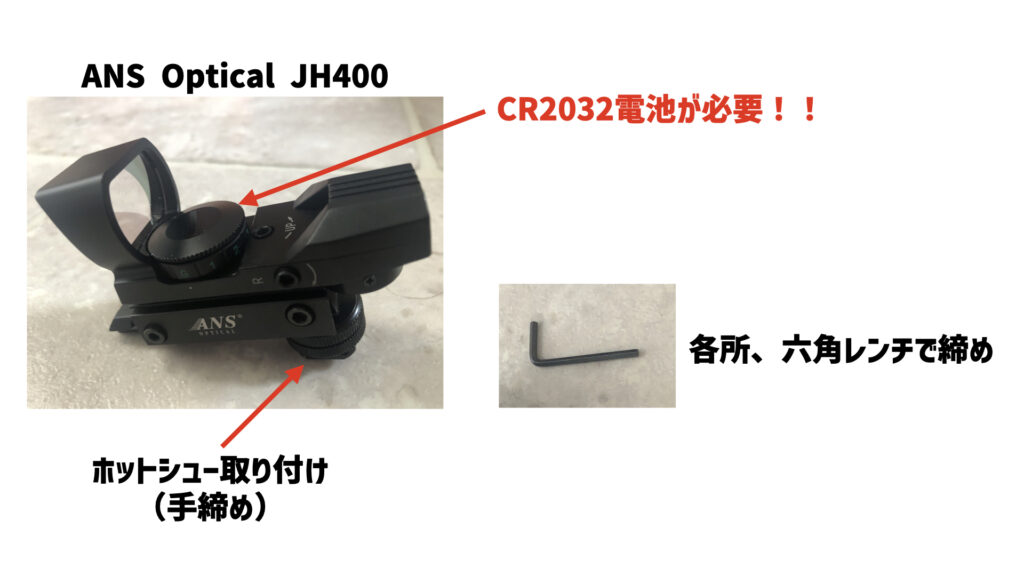
カメラにはホットシューを介して取り付け、手で締めるだけで固定できます。
六角レンチはフロントサイトの左右上下の位置調整で使用します。(※カメラの光軸あわせ用)
普通はカメラボディ上部のホットシューに取り付けますが、ホットシューマウントで照準器の取り付け位置を調整することができます。
また、両眼視と呼ばれるファイダーと照準器を同時に覗き込む位置に取り付けるテクニックなどもあります。

照準器を使う際は、カメラ側の液晶モニターやファインダーを見ずに、照準器のレティクルを見て写真を撮ります。
フロントサイトに表示されるレティクルは色、濃度、形が変更できます(下の調整図参照)。
照準器のレティクルで捉えた被写体が、カメラ側の画角の中心にくるよう、光軸あわせをしないといけません。
照準器の光軸合わせには六角レンチを使用します。

基本的には、照準器は電源を入れてレティクルを表示させたら、光軸をあわせて写真を撮るだけですので、とくに難しい操作を覚えるといったことはないです。
照準器の光軸合わせ
光軸合わせのについては、私よりはるかに優れた解説記事やYoutube動画がありますので、そちらを参考にされたほうがいいです。
私も以下のコンテンツを参考に、光軸合わせの方法を習得しました。
先ず、目標となるものを適当に決め、それにレティクルを合わせ、AFしてシャッターを切ってみます。
撮影写真を確認して、どこにピントが合っているか確認します。
レティクルの左側にピントがあっていれば、六角レンチでR→の表示がある六角穴付きビスを矢印と反対方向に回します。
そうして位置調整を地道に行い、最終的にレティクルと撮影写真のピントがあえば光軸合わせは完了です。
参考に、私が視聴した動画や記事をいくつか載せておくので、どうぞ
Youtubeでは検索例「照準器 合わせ方」などです。
また、撮影する被写体との距離も光軸合わせする上で重要なファクターとなるようです。
本記事で紹介する照準器は5000円以下の安い照準器ですが、有名な照準器ですと、オリンパスドットサイトEE-1、キングフィッシャー、SONIDORIドットサイトがあります。
照準器の使用頻度が上がり、良い照準器が欲しくなったら購入を検討ですかね。
照準器を使う意味と使ってみての実感
そもそもなんですけど、私はなぜ照準器を使うのだろうと疑問に思っていました。
それは私がこれまでズームレンズを使っていたがゆえに気づかなかったことだと今になって思います。
焦点距離の長い望遠や超望遠の単焦点レンズを使っていると、ファインダーを除けばそこはもう超望遠の世界で、被写体はどこ?どこ見ているかわからん!ってなってしまいます。
また、動きのある被写体を追っている時は、余裕でフレームアウトしてしまいます。
しかし、照準器を使えば、いつも見ている視点で、それもファインダーを覗き込まずに、シャッターを切ることでできるのです!それゆえ、超望遠単焦点レンズであっても難なく写真が撮れると言うわけです。
慣れていれば照準器なしでも撮影できるかもしれませんが、不慣れな人や、野鳥の貴重な瞬間を狙うような人にとっては歩留まりを高める意味でも、照準器は必要でしょう。
カワセミで試し撮り
今回はカワセミを例に照準器を使って撮影してみます。
カワセミが来る前に現地入りし、機材のセットアップと同時に照準器の光軸合わせをすませておきます。
街のカワセミは警戒心が薄く、サービス精神が高いため、ブラインドを張らなくても撮影できます。
使用機材はEOS 7D MarkII + EF100-400mmL II型です。
焦点距離は400mm固定とし、ズームリングで被写体を追わずに、照準器頼りで撮影します。

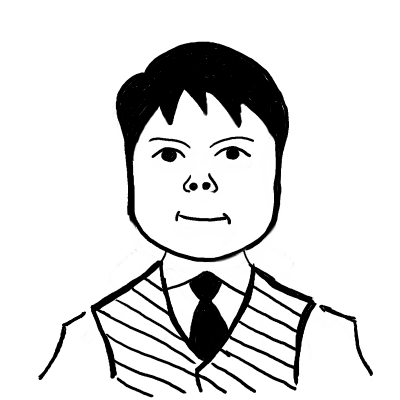 Isamu
Isamu

照準器で撮影した作例「カワセミ」
こんな感じで水面スレスレを飛行するカワセミをパシャリです。

たまにピントが外れるときもあります。

ピントが外れても、再びピント食いつき撮影できます。
Canon EOS 7D MarkII+EF100-400mmL II型レンズが優秀だからかな?

餌をゲット!
すぐ食べずにどこかに運んていったことから、子育ての最中だったのでしょうか

ふー!かっこいい〜

ピントがあったりピントが外れたり、照準器を信じてシャッターを切っているので、撮影した写真を確認するまでわからないドキドキ感がたまりません。

翼全開!

地面と水平飛行!

あぁ〜またピントが外れる…

ダイブ後、無事お魚をゲットしたカワセミ!!
おめでとう!

餌運搬お疲れ様です。

製品情報
今回、記事で紹介した照準器は、Amazonで¥3,976(2022年8月時点)で販売されています。
同じメーカのANSからはコンパクトタイプやフロントサイトが丸形のタイプの照準器が販売されているので、照準器を使ってみたい方は予算¥5,000ほどで購入できます。
まとめ
ANS Optical JH400は5000円以下で手頃に導入できる照準器であり、野鳥の飛翔写真を撮影するにはちょうどいいと思います。
私の野鳥撮影もとまっているものから、飛んでいるものにステップアップしてきました。
照準器をうまく使いこなして、PC画面で見返したときにうっとりするような野鳥写真を撮りたいですね。
カメラ機材に関する記事を書いているので、興味ある方はご覧になってください。
 14,500ショットしたのでCanon EOS 7D MarkIIを語ります
14,500ショットしたのでCanon EOS 7D MarkIIを語ります
 至高の野鳥撮影レンズ・Canon EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM
至高の野鳥撮影レンズ・Canon EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM
 Sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Sports テレコンキットで超望遠デビュー!
Sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Sports テレコンキットで超望遠デビュー!
 Sony高画素フルサイズミラーレスILCE-7RM3(α7R III)導入!
Sony高画素フルサイズミラーレスILCE-7RM3(α7R III)導入!
 Sony超望遠レンズ・FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS(SEL200600G)
Sony超望遠レンズ・FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS(SEL200600G)
7DMarkII Canon EF70-200mm EF100-400mm EF400mmf4 EOSR7 EOS RP FE200-600mm FEマウント ILCE-7RM3 ILCE-9 Instagram K-S2 PENTAX Sigma150-600mm SKYLUM SNS戦略 Sony TAMRON α7RIII ズームレンズ ツキノワグマ ドットサイト ネイチャー フィーチャー フォトコン フォトコンテスト プリント ミラーレス ミラーレス一眼 レビュー 一眼レフ 仁別 写真 写真展 写真現像 動物 望遠レンズ 照準器 秋田 自然風景 超望遠レンズ 野生鳥獣 野鳥 風景