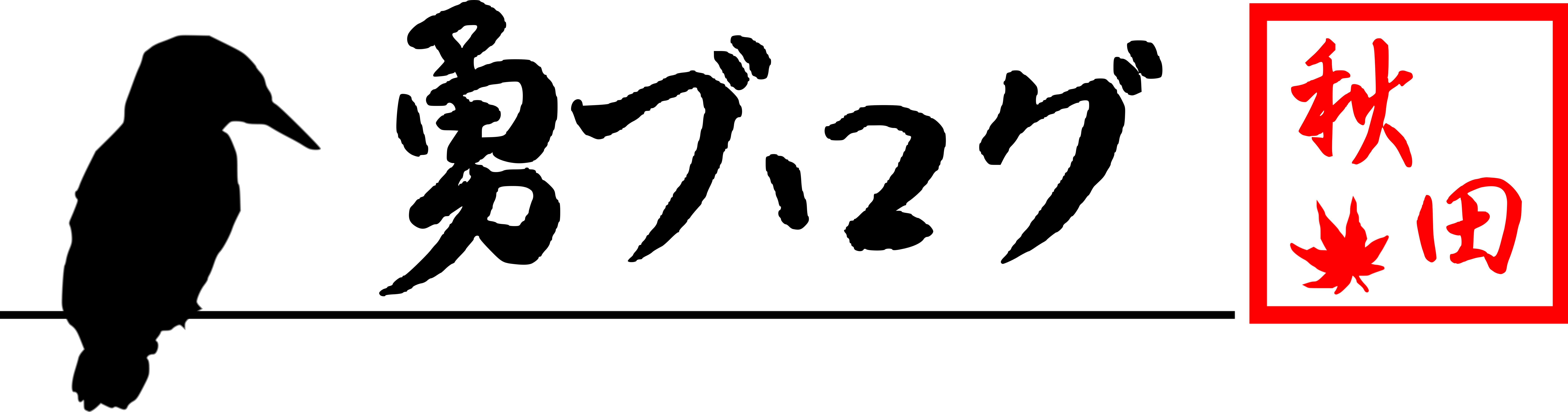「知らないことは怖いこと」
クマ関係者にツキノワグマとヒグマどちらが怖いか尋ねると、ヒグマ関係者はツキノワグマが、ツキノワグマ関係者はヒグマが怖いと答えるそうです。ツキノワグマを観察している私はツキノワグマに対してそれほど恐怖を抱いたことはないですが、ヒグマは怖いと思っています。きっと、両方をよく知らない一般人の方は、両方が怖いでしょうね。おそらく、知らないことは怖いことなのだと、考えさせられます。
狩猟生活 2024, Vol.18より一部引用
連日のクマ出没の報道が各報道機関からなされていて、怖い思いをしている方もいるでしょう。報道の中には「クマが襲ってきた」とクマが人を好んで襲う動物であるかのように印象づけているものもあり、それに対して疑念を抱いております。私は”クマは人を積極的に襲う動物ではない“と考えており、これは私のこれまでの300回以上のクマとの遭遇経験から着想したものです。これだけ多くのクマに出会ってきた私ですが、クマが私に対して向かってきた・襲ってきたことはありません。ではなぜクマは人を襲うのか、襲ったという事実の背景には、人と出会ったときの状況、子グマを連れた親子グマだったのか、人に出会う前に何かあったのか、など様々な要因が関係して、クマは人を襲わざるを得なかったのでしょう。ここでは、私のこれまでのクマ観察に基づき、クマを深く知るための有益な知見を提供するとともに、記事題目にもあるようにクマに関わる問題について記述してみようと思います。

こんにちわ、勇です。
今日は、いま日本で話題になっているクマの問題に関わる「クマ目撃・出没マップ」の”意義”と”懸念事項”についてまとめてみました。
これを考えることになったキッカケは、山に通う途中、山麓の集落を通るのですが、クマを見に来たであろう車(不審車両?)をよく見かけるようになったからです。
◯月◯日にどこどこでクマが出没した、という情報をマップを使って確認して来たのでしょうか。
クマに会わないように気をつけることがマップの本来の使い方だと思うのですが、クマを見たい、という好奇心だけでクマに関する知識を持たない者が本来の使い方を逸脱してマップを利用し、クマを近くで見ようとするのは危険極まりないです。
本記事では、このクマ目撃・出没マップの意義を改めて確認するとともに、現在懸念されている事項を抽出して問題提起してみようと思います。
目次
クマ目撃・出没情報マップとは
クマの目撃・出没をリアルタイムで確認するため、各自治体で提供されているのがクマ目撃・出没情報マップです。
名称は自治体ごとにユーモアな名前が多く、例えば、北海道のヒグマ目撃マップは”ヒグマップ”と呼ばれています。
私の住む秋田県では、クマダスという気象庁のアメダスをもじったツキノワグマ等情報マップシステムが提供されています。
自宅近くにクマが出没していないか、安全確認のため、私も利用しています。
クマダスでは、自分の住む市町村を選択してメールアドレスを登録して配信設定すると、自分の住む市町村にクマが出没した時(クマ出没の投稿があった時)、メールで連絡が来る仕組みとなっています。
このため、私がメール確認を怠った時以外、ほぼリアルタイムでクマの出没を確認できる状況にあり、クマとの遭遇を回避できていると実感しています。
利用意義 ークマ出没の情報の入手と遭遇回避ー
クマ出没・目撃情報マップでは、クマが出没した、クマを目撃した場所を投稿すると、Googleマップなどの地図上に投稿した情報が表示されます。
この情報マップシステムを大衆が利用することによって、利用者全員が目となり、ツキノワグマの目撃情報を共有できます。このクマの目撃情報の共有とそれによって利用者がクマと回避する可能性が高まることがクマ出没・目撃情報マップの利用意義だと考えます。
自治体の担当者だけだと、クマの出没の確認と目撃数は限られてしまいます。一方、このツキノワグマ等情報マップシステムを大勢の市民の方が利用すると、クマの目撃・出没情報が投稿されて、クマの動向が共有されることで、クマとの遭遇リスクを低下させることができます。
さらに、クマ目撃・出没情報マップ上に多くの出没情報が山積することで、クマ出没に関する情報の精度も高くなってきます。
なるべく多くの人々にクマ目撃・出没情報マップを利用してもらうことで「マップ上でのツキノワグマの出没情報の共有およびクマによる事故の未然防止」につながります。
懸念事項
クマ出没後、そこに留まっているのか判断が難しい
クマ出没・目撃情報マップでクマ出没を確認した後、同じクマがそこに1時間後、1日後、1週間後もそこにいるか考える必要があります。
しかし、クマの食べ物、生態、生息環境などのクマ知識に明るくない方にとってはその判断は難しいことであるのも事実です。一般人はそこまで深く思考しないのですが、クマとの遭遇を回避する確率を高めるためにも、クマ知識を少しでも蓄えて、クマに会わないためにどうすればいいのか考えて欲しい次第です。
クマが同じ場所に居続けるのか、居続けないのかを考えるために、クマの行動をまず予想しないといけません。これまでの私の経験から、クマに出くわした時、その時のクマの行動は以下2通りだと思います。
1.どこか向かう場所があって移動の最中
2.食べ物に寄ってきて遭遇場所にたどり着いた
1の移動の最中であった場合、人に気づかずスーッと通過、もしくは人に気づいてダダダッ!逃走して、どこか別の場所に向かうため、その場所には戻ってこないです。
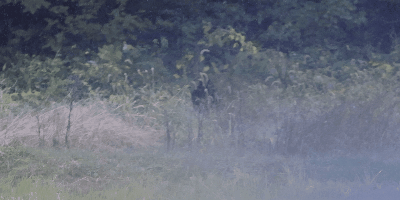
2は食べ物、例えば、畑の農作物やりんごや柿などの果物、栗などに寄ってきて、その食べ物がなくなるまで食べ続けて居座る状態です。

1か2どちらかを判断するには、クマだけを見るのではなく、周りの環境(川の近くか、どんな木々が生えているのか)をよく観察することが大事です。
川の近くであれば、川沿いに移動することも考えられますし、人の背丈ほどの草藪が道路の両脇にビッチリ生えていると、そこに身を隠して移動することも考えられます。
川沿いにクルミの木が群生していれば、このあたりはクマが登りそうだなと、クマが来ることも予想できます。地形やクマの食べ物を見分けられることで、クマの出没予測にも繋がるのです。
コメントで自慢する人の存在
クマダスの場合、投稿された出没情報には日時、場所、頭数などに加えて、コメントを自由に書くことができます。
過去に見た投稿で、車から降りてクマを撮ってみた、という投稿がありましたが、管理者に注意されていました。クマを撮ったと自慢したい気持ちもわからなくもないですが、安全な車から降りてクマに接近する危険行為はやめましょう。
さて話を進めますが、出没情報の投稿のコメントを読むことで、クマがそこに居続けるのか、ヒントを得ることもできます。
私が意識してみるコメントは、クマが◯◯の木に登っていた、と書かれたものです。◯◯には、クルミや栗、柿などが入ります。これらは晩夏から晩秋にかけて人里で実る、クマの食べ物になります。
この投稿を見かけた場合は、この場所にクマがまた来そうだな、と予想することができます。もし自宅近くでこのようなコメントを見かけたら、その場所付近には近づかないほうが無難でしょう。
クマ目撃情報のコメントは、クマの動向を知るための目撃者の貴重な情報を伝える機能ですので、クマ出没情報を投稿する人は面倒かもしれませんが、クマを見た、だけでなく、何をしていたのか、どこに居たのか、ちょっと情報を付け加えるだけで、その情報を見る方々にとってクマの動向予想を助けることになります。
ただ、ざっくりとした内容しか書かれたコメントも散見されるので、状況や環境に関する情報は手に入りにくいですが、読まないよりは読んだほうがためになると思います。
まとめますと、危険な行動をして管理者に注意を受けているようなコメントは武勇伝なので参考にならないのと、できるだけ詳しく状況が書かれた投稿はクマの動向予測を助ける貴重な情報源となることを覚えておいてください。
フィルター機能の使い道
秋田県の野生鳥獣の目撃に関するマップシステムに関して、クマダスの前身は「野生鳥獣目撃マップ?」確か記憶ではこのような名前だったと思います。
これもクマダスと同じようなシステムで、クマやシカ、イノシシの目撃情報を投稿して地図上に反映させるものです。
このクマ出没・目撃情報マップがクマダスとして新しくなったわけですが、クマダスになってからフィルター機能を使用できるようになりました。
フィルターでは、月日、市町村、獣害種、情報種別(目撃、人身被害、痕跡)の項目から、自分の表示させたい項目にチェックを入れて、フィルタリングできます。
多くの方は、市町村にフィルターをかけて自分の住んでいる地域の付近にクマが出没していないか、確認するぐらいだと思います。
参考までに、私の場合で”月日”にフィルターをかけてクマの出没を確認する例を紹介します。
なぜ月日でフィルターをかけるかというと、クマの行動は季節によって変化するからです。
たとえば、栗は9月中旬から10月中旬にかけて実るので、それを食べにクマが集まってきます。逆をいえば、9月より前の月(栗が実る前)や10月末(人が拾ったり、クマが食べた後)では、クマをあまり目撃しなくなります。
そのため、栗の時期になる前に、前年の9月中旬から10月中旬でフィルターをかけてみて、どこでクマが多く目撃されたのか確認します。そうすることで、クマが多く出没する場所が予測でき、上記の時期にはそこに近づかないのが無難と判断できるわけです。

また、他の堅果類(ブナ、ミズナラ、コナラ)の豊凶もクマが栗の実を食べに集まることに関係しています。
栗は豊凶が少なく、毎年実をつけると言われています。しかし、豊凶の激しいブナや、ミズナラやコナラなども毎年実をつけるわけではないです。
これらの堅果類は里山・奥山に生えていますので、ブナやミズナラが豊作・並作の年はあまり人里にクマが下りてきません。一方、ブナ・ミズナラが凶作で、山にどんぐりが”全くない”となると、クマは人里に栗を食べるために降りてきます。
ブナは毎年7月を過ぎたあたりでブナの開花・結実調査が林野庁で公表されます。秋田県は、ブナやミズナラの豊凶調査の結果をHPで公表しています。
また、私は4月から5月にかけてブナなどの花が咲いたのか、自分の目で確かめるようにしており、その年の堅果類の結実を予想するようにしています。
そして、集めた情報を参考にして、今年はブナが大凶作だから人里にクマが大出没する可能性がある、気をつけないと、と注意を払うようにしています。
秋田でクマが大出没した2023年では、ブナの大凶作に加え、ミズナラやコナラなど他の堅果類も軒並み凶作だったのではないかと言われています。そのため、秋に人里にクマが大出没したのです。
また、2023年は栗に関して予想外の出来事が起こりました。まだ青い成熟していない栗を食べに栗に木に8月末から9月上旬の段階でクマが木に登ったのです。これはあまりにも早い出来事です。

この年はクマの食べ物がまったくなかったので仕方がない選択だったと思います。このことからも、ブナの豊凶、それ以外にもクマの食べ物になる果実や堅果類の実り具合で、クマの行動が変化することが考えられます。
長々と話しましたが、フィルター機能は、季節ごとのクマの動向を予測するための便利機能であることには間違いないですが、クマの食べ物の状況によっては予測を外してしまうこともあるので注意が必要です。
ただ、クマの食べ物を知っていないとフィルター使っちゃいけないんだと誤解しないようにしてください。だいぶマニアックに書きましたが、クマの食べ物を知っていなくても、前年の同月と前後1ヶ月でフィルターをかけてみると、クマの出没具合も大分把握できると思いますので、ぜひクマとの遭遇回避にフィルター機能を活用してみてください。
クマに会いたい好奇心が強い素人の望まれない訪問
ツキノワグマ等情報マップシステムの利用が始まり、マップ上にクマの出没・目撃情報がポツポツ、とあがってきます。
そうすると、マップ上でクマの出没情報を見た人は次のことを考えると思います。
1.怖いな。その場所には近づかないようにしよう。
2.ここにクマが出たんだ。見に行ってみよう。
クマ出没・目撃マップは「自分以外のクマを目撃した人から共有された情報を確認し、クマに会わない行動を心がける。」ことが本来の使い方と認識しています。上記の1の場合ですね。
最近、このツキノワグマ等情報マップシステムをもとに、クマが多く出没している位置を確認して、そこの地域外からわざわざ訪問する方が増えています。2の場合ですね。
私は春から秋にかけて毎週末、山に通っていますので、その時に山麓の集落を通過するのですが、そこで見慣れない車両を見かけます。時には、民家のすぐ横に車を駐車して、じっと何かをしている様なので、もう不審車両です。
ツキノワグマ等情報マップシステムを見てクマを好奇心で見に来た方なのか、それとも何か別の理由で停めているのか、いづれにせよ理由は不明ですが、秋になってからクマを見に来たであろう方が本当に増えてきました。
それゆえ、クマ出没・目撃マップの好ましくない使い方による懸念は大きいと考えています。
また、もしクマを見つけて写真や動画を撮ることができたとします。その後、SNSなどに地名付きでアップロードされようものなら、さらに多くの方がその場所に来てしまい地域の方は大変迷惑します。
その誘引されてきた野次馬さんがSNSにアップした投稿を見て来たのか、これは証明も難しく、彼らはきっとツキノワグマ等情報マップを見てきた、と嘘をつくでしょう。
正しい情報リテラシーを持ち合わせていなく、マップの本来の使い方を逸脱してクマ探しに使う、こうした方がクマ出没場所に来ることは、地域の方とのトラブルも起こす可能性があります。
地域の方に話を伺うと「ここの地名を出さないでほしい」皆口を揃えて言います。この一言の裏には、私がいま説明した地域の人とのトラブルの未然防止と、好奇心で来た人がクマに襲われるのを懸念していることが推察されます。
人に見てもらいたい、この気持ちはわからなくもないですが、地域の人のことを考えるなら、地名を出した身勝手な情報発進をやめたほうがいいですよ。
不適切な投稿?
不適切、という言葉が適切かどうか迷うところですが、クマダスを見ていると時折、登山道にクマが出た、という投稿を見かけます。
まず、山なのでクマは当たり前にいます。クマの住む場所にお邪魔させてもらって登山しているので、当たり前のことです。
クマダスに投稿する前に、適切な所に確実に通報してください。通報した上でクマダスにも載せているかもしれませんが、登山道でのクマ出没情報はややベクトルが違うと思います。
クマダスは町中など人の生活圏に出没したクマの目撃情報を投稿することに徹するべきだと思います。人が普段の生活を送る上で、クマの出没に関する情報を入手し、クマの人身事故を未然に防ぐことがクマダスの利用意義なのです。
登山者の方は、クマが登山道など山で出会った場合は、通報すべき場所に通報すること、YAMAPなどの登山情報プラットフォームサービスを使って登山者同士で共有したほうが、登山者の人身事故の防止にも繋がるのでベストな判断かと思います。
最後に
クマ出没・目撃情報マップは、クマの出没に関する情報を共有・入手でき、未然にクマによる人身事故を防ぐための重要なツールであることを確認しました。
懸念事項として、マップの出没情報からのクマの行動予測が困難、フィルター機能の使い方、投稿情報のコメントでの自慢や投稿情報を見てクマを見に来る人の増加、不適切な投稿、など多くの懸念を抱えております。
ただこれらは、利用者が正しい使い方を理解し、常識を持って利用することで改善が見込めるものです。正直、現状のクマ出没・目撃情報マップは利用者の民度に依存している状況にあるので、目的を見誤らずに、クマとの遭遇を避けるための有効ツールとして皆さん活用することを切に願っています。
最後までご覧になってくださいまして、ありがとうございました。
このブログでは、秋田の自然・野生鳥獣に関する記事を公開していますので、興味のある方はぜひご覧になってください。
 初夏から初秋にかけて出会った野鳥たち
初夏から初秋にかけて出会った野鳥たち
 渓流ヤマセミ巡り2025
渓流ヤマセミ巡り2025
 オオワシ観察 2025年[年始〜暮春]
オオワシ観察 2025年[年始〜暮春]
また、YouTubeでは、クマに関するショート動画をアップしていますので、クマの生態を見てみたい方はぜひご覧になってください。
今後とも勇ブログをよろしくお願いいたします。
最近、クマの人里への出没が増え、人々の安心した暮らしが遠のいた気がします。クマはなぜ人里に出没するようになったのでしょうか?秋田県では少し前までクマの生息頭数は1000頭前後と推定されてきましたが、推定方法をより精度の高い方法を採用したところ2800〜6000頭のクマが生息していることが明らかになりました(ツキノワグマの生態と人身被害防止より)。かなり多くのツキノワグマが秋田に生息しているのですね。
山に食べ物が豊富な年、例えばブナが並・豊作の年は、多くのメス熊が冬に出産することから、翌年はベビーラッシュとなって爆発的にクマの数が増えます。一方、クマの狩猟を行うマタギ・ハンターの高齢化問題によってクマの個体数管理が行き届いていない現実があります。また、奥山へと通じる主要な林道は数年前の豪雨で通行不能となり、規模の小さな林道は藪化によって入れなくなっています。林道に入ることができないと、山の状況もよくわかりません。かつクマは人間が入ってこないので、こうした不通の林道はクマの巣になります。こうした、いくつもの要因が積み重なって、クマと人間の距離は徐々に離れ、クマの繁殖がクマの自然減・駆除数を上回っていると考えられます。従来奥山でひっそりと暮らしていたクマたちですが、奥山に増加したクマが収まることができなくなり、その生息域を徐々に広げてきたのではないでしょうか。
人里に出没したクマを駆除することは、クマの頭数削減に直接的に貢献するものですが、クマの出没そのものを防ぐ効果的な策とは言えません。クマが出没してしまったら、そこにはクマが出没する導線が形成されていることが示唆され、周辺の環境を変える必要があります。現在、里山には杉や檜が高密度に植林され、かつて美しかった景観が失われています。野生鳥獣にとっても高密度な針葉樹林は生息に適さないことが分かっており、食べ物も少ないことから、ただ人間に花粉症を引き起こさせる負の遺産であることは間違いないです。事業性は乏しいですが、針葉樹を伐採し、広葉樹を植林して森を再生させることで一昔前の景観が復活し、観光資源の再創出と野生鳥獣たちの住処を提供することが可能です。
我々は今一度、クマの住処である森についてその環境をよくよく考える必要があります。
これまでに私が読んだツキノワグマの知識を深めるための書籍
- ツキノワグマのすべて、小池伸介著、澤井俊彦写真提供、分一総合出版、2022年出版 ★おすすめ★
- ツキノワグマの生態学、信州大学山岳科学総合研究所、オフィスエム、2011年発行
- わたしのクマ研究、小池伸介著、さ・え・ら書房、2017年出版
- ある日、森の中でクマさんのウンコに出会ったら、小池伸介著、辰巳出版、2023年出版
- 人を襲うクマ、羽根田治著、山崎晃司解説、山と渓谷社、2021年出版
- 人狩り熊、米田一彦著、つり人社、2018年出版
- ツキノワグマ、宮崎学著、偕成社、2006年出版
- 「クマの畑」をつくりました、板垣悟著、地人書館、2005年出版
- ツキノワグマを追って、米田一彦著、小峰書店、1994年出版
- ツキノワグマ、山崎晃司著、東京大学出版会、2017年出版
- 滅びゆく森の王者ツキノワグマ、皮膚件哺乳動物調査研究会編著、岐阜新聞・岐阜放送、1993年発行
- 山でクマに会う方法、米田一彦著、山と渓谷社、2011年出版
- ツキノワグマのいる森へ、米田一彦著、丸善、1999年出版
- クマが樹に登ると、小池伸介著、東海大学出版会、2013年出版
- 写真集 秋田市にはクマがいる、加藤明見、無名舎出版、2018年出版
7DMarkII Canon EF100-400mm EF400mmf4 EF500mmF4LISIIUSM EOSR7 EOS RP FE200-600mm FEマウント HOKUTO ILCE-7RM3 ILCE-7RM5 ILCE-9 Instagram K-S2 PENTAX R5MarkII Sigma150-600mm SKYLUM SNS戦略 Sony TAMRON α7RIII オオワシ ツキノワグマ ネイチャー フィーチャー フォトコン プリント ミラーレス ミラーレス一眼 レビュー 一眼レフ 仁別 写真 写真現像 動物 望遠レンズ 海鷲 秋田 自然風景 超望遠レンズ 野生鳥獣 野鳥 風景