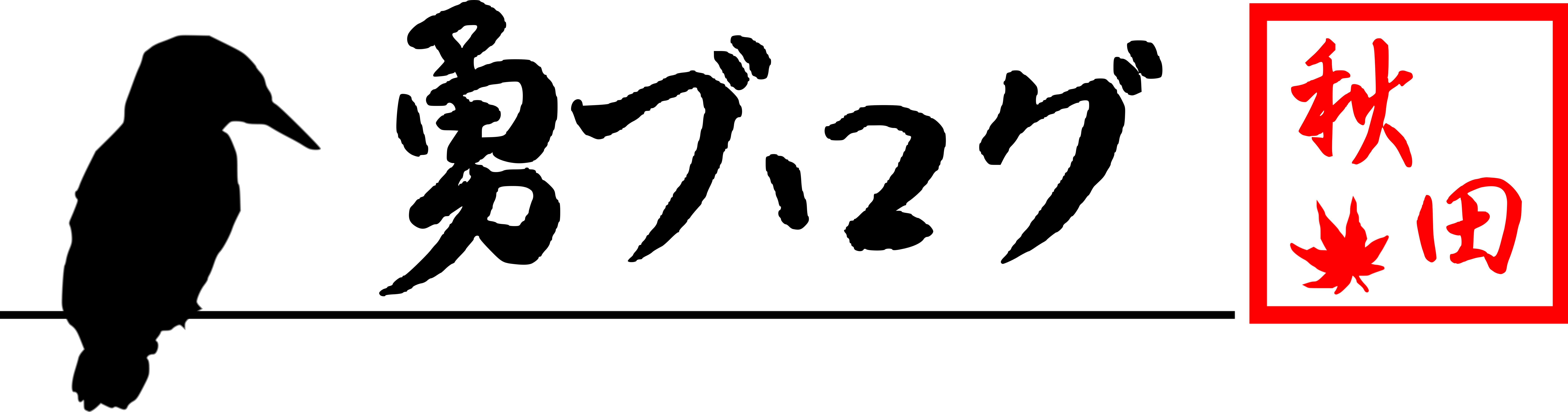こんにちわ、勇です。
今夏もツキノワグマを観察する機会にそれなりに恵まれました。普段あまり知ることのないクマの生態について書き記すと共に、撮影したクマの写真を公開します。
目次
早朝に活発に活動するクマたち
人里近くではクマたちは夜行性になると言われています。日の出前の薄暗い中、移動している姿をよく見かけます。

クルミの木の下で食事中だったようです。クルミの渋で顔を歪めているのか、それとも元々こういった顔なのか、ちょっと顔が歪んでいてブサイクですね。
現像で露光を大分上げていますが、実際はかなり暗めのシーンで撮影です。フレキシブル拡張スポットでクマの顔にピンポイントで顔を合わせて撮っています。

草むらからヌッとクマが起き上がりました。このような草むらで寝るのか、2023年にも茂みにクマの寝た痕跡を見つけたことがあります。こんな場所で寝るのかと、今日もまた新しい発見がありました。

中型のクマが木に登ってクルミの枝を折ったり、実を地面に落としたりしていました。

田んぼの奥にツキノワグマを発見しました。小さなクマだと稲の背より低いため、よ〜く見ていないとクマがいるのに気づきませんね。
ここまでの写真はフレキシブル拡張スポットのAFフレームで合焦させて撮っているか、手前にピントをもっていかれそうなシーンの場合、DMFで即座にピント合わせして撮っています。ミスショットもありうるので、数撃ちゃ当たる戦法で写真をたくさん撮ってその中から使える写真をセレクトしています。
森の中でクマが熟睡
オニグルミの木が群生する川沿いで、クルミの木上にクマがいました。観察途中で気づかれましたが、同じ木でクルミを食べたり、眠ったりしていました。

じっとこちらを見ています。クマを見ていると、時折、こちらと目を合わせてきます。彼は間違いなく、我々を認識しているのです。ここで目を逸らしたり、背を向けて逃げるのは大変危険です。
このように枝や葉がごちゃごちゃした所では、DMF(ダイレクトマニュアルフォーカス)を重宝しています。最初のだいたいのピント合わせはフレキシブル拡張スポットで行い、その後DMFでピントを微調整してシャッターを切っています。

また、目が合いました。常に目を合わせてくるわけではありませんが、定期的にこちらの様子を伺っているようです。

木の上でじっとしていると、クマがいることになかなか気づけないですね。
クマに気づく時は大抵の場合、木を折って大きな音がしたとき、勢いよく木から降りてきたとき、鳴き声を出しているとき、などです。行動でいえば、食事中や警戒中のときです。

顔や耳が丸っこいのが特徴ですね。最近見たクマの中では、ダントツで可愛いですね。

しばらくこちらを見ていた後、クルミの実を狙って枝先の実を引き寄せています。

クルミを口に含んでいます。クルミを食べると、渋で口の中が真っ黒になります。そして、今丁度クルミが口の中にインしていますね。

口に含んだクルミを砕くため、かなりの力でクルミの殻を噛み砕いているようです。かなり踏ん張っているのか、鼻のところにすごいシワが入っています。

しばらくクマを見ていると、木の上にジャストフィットしてダラダラし始めました。

なんとここで、クマが寝始めました。この後も、クルミを食べては寝てのサイクルを繰り返しており、観察できたのは僅かな間でしたが、クマはこのように食べ物のあるところで食事と睡眠を繰り返しているのだろうか。
今シーズンのごちそう”栗”に集うクマ
私の2年前(2023年クマ大出没)の記録では、10月上旬にクマが栗につきました。今年は、それよりも2週間ほど早い9月中旬から下旬にかけて、クマが栗の木に登る姿を確認しました。

カケスが栗を加えています。初めてみました。地面に落ちた実は他の動物たちによっても貴重な食べ物となるのかな?

山奥の人が住んでいない廃屋の近くの栗の木に現れたクマです。地面に落ちた栗を一生懸命食べていました。栗は地域によって成熟度合いに差があるのか、イガが茶色になって地面に落ちいてる木もあれば、他所ではまだ緑色のこぶりなイガがついた木もあって、後者は成熟までもう少し時間がかかるのかな、と見ています。
この栗の成熟にバラツキのあることは、長期間に渡ってクマが栗の木に居着くことを予想させられます。

まだ成熟していない緑のイガを爪で器用に開き、未成熟の栗の実を食べていました。
今年は山にクマの食べ物となる堅果類が少ないからか、たとえ未成熟であっても手当たり次第に食べ物を食べているという感覚です。
親子クマの大量出没と栗への依存
今年はお盆前まではクマの姿を時折見かける程度でした。ところが、お盆を過ぎた後、どこにいたんだ、と思うくらい親子クマを目撃するようになりました。今冬の出産でたくさんのクマが生まれていたようです。

子グマの行動に目を配りながら、栗を食す母グマです。小〜中サイズの母グマですが、しっかり仔を2頭連れていました。
このような開けたシーンでは、フレキシブル拡張スポットやゾーンでAF頼りでピント合わせシャッター切りしてます。

子グマはやんちゃでお母さんをほっといて、木に登りだしました。母グマは子グマにもう行くよ、と合図しても子グマはまだ登ってたいもん、と駄々をこねていました。
このように被写体がしっかり認識できる状況では、瞳認識が発動して瞳にしっかりとピントを合わせてくれます。クマは暗がりだと黒の塊にしか見えないので、認識してくれるか疑問でしたが、瞳にピント合わせをしていて流石だなと思いました。

撮り方によっては母グマが大きく見えます。実際はそれほど大きくなく、中程度からやや小さいクマだな、という印象です。

栗の木に親子3頭が集まっています。地面に落ちた枯れ枝は、以前もクマが木に登り枝を折って地面に落とした証拠です。
どのクマにピントを合わせればいいか迷いましたが、奥をぼかして手前にピントを合わせることを選択しました。

母グマは警戒を怠りません。こちらにお尻を向けていても、時折、こちらを向き、目を合わせることを忘れません。こりゃ菜々緒ポーズだな…
クルミ・栗・稲の三重奏
栗に登り始めるのが9月中旬と早い時期から確認しておりました。栗と同時にまだ残っているクルミにも、クマが集まっていました。

まだ薄暗い中、栗の木に登ってきたクマです。こちらをじっと見てきましたが、私もじっと動かずに静止していると、枝先を目指して登り始めました。
現像で無理やりピントがあったかのように見せています。実際は、ほぼ真っ暗でその中を動く黒の塊にピント合わせしましたが、まったくピント合わないっす。

栗を食べているクマもいれば、クルミを食べているクマもいます。彼らには好みがあるのか、それとも地域性か縄張りの関係か、いづれにせよ、クマの行動も一意に定まらずに主に3種の食べ物に依存した状況が2〜3週間ほど続きました。
DMFでピント合わせしましたが、捕食シーンを撮ることを優先してピン甘でシャッター切っています。設定にレリーズ優先、ピント優先がありますが、私は迷わずレリーズ優先です。完璧にガチピンの写真が撮れなくてもクマとの出会いは貴重なのでその瞬間を絶対に写真を収めたいと思う次第です。

日の出前、田んぼ近くに佇んでいたクマ親子です。私もどんくさいので、クマが立ち上がる瞬間をこれまで捉えられてなかったのですが、今回始めてその姿を撮ることができました。
ただ、暗いシーンだとAF方式の関係か、サーチ駆動してしまうので、それを感じ取ったらAFを中断してDMFでピント合わせして、撮っています。
最後に
朝方のクマ撮影は「暗がり+真っ黒な被写体」で苦慮しております。ミラーレスカメラになって被写体認識に頼れる状況になってはきましたが、原始的なMFでのピント合わせが数秒しかチャンスしか与えられないクマとの遭遇・撮影においては有効という状況です。
初夏から秋にかけてクマの生態に迫れたシーズンでした。春、夏のブナの開花・結実調査からも分かっていたように、やはり秋が近づくにつれて山に食べ物がなくなり、クマの行動範囲拡大と山麓集落への出没が起きています。
特に今シーズンで印象的だったのは、9月中旬から10月中旬にかけてクルミ・栗・稲の3種にクマが引き寄せられていたことです。クマの食べ物にバリエーションがあったため、行動が単調ではありませんでした。
ここからさらに季節が進むと、クルミと栗が終わり、稲につくか、柿につくことが予想されます。このクマの食べ物事情は2023年を彷彿とさせます。街にクマが大量に出てくることが予想されますので、皆さん十分に注意してください。
最後までご覧になってくださいまして、ありがとうございました。
このブログでは、秋田の自然や野生鳥獣など、ネイチャーを題材に写真を撮影しています。また、ツキノワグマや特定の鳥類に関しては熱心に観察を行っており、その観察から分かった生態などについて情報発進していければと思います。
 クマ目撃・出没情報マップの意義と懸念事項
クマ目撃・出没情報マップの意義と懸念事項
 夏の撮影・青と赤のキングフィッシャー!
夏の撮影・青と赤のキングフィッシャー!
 オオワシ観察 2024年[立冬〜年末]
オオワシ観察 2024年[立冬〜年末]
 渓流ヤマセミ巡り2025
渓流ヤマセミ巡り2025
 秋田県美術展覧会
秋田県美術展覧会
最近、クマの人里への出没が増え、人々の安心した暮らしが遠のいた気がします。クマはなぜ人里に出没するようになったのでしょうか?秋田県では少し前までクマの生息頭数は1000頭前後と推定されてきましたが、推定方法をより精度の高い方法を採用したところ2800〜6000頭のクマが生息していることが明らかになりました(ツキノワグマの生態と人身被害防止より)。かなり多くのツキノワグマが秋田に生息しているのですね。
山に食べ物が豊富な年、例えばブナが並・豊作の年は、多くのメス熊が冬に出産することから、翌年はベビーラッシュとなって爆発的にクマの数が増えます。一方、クマの狩猟を行うマタギ・ハンターの高齢化問題によってクマの個体数管理が行き届いていない現状があります。また、奥山へと通じる主要な林道は数年前の豪雨で通行不能となり、規模の小さな林道は藪化によって入れなくなっています。林道に入ることができないと、山の状況もよくわかりません。かつクマは人間が入ってこないので、こうした不通の林道はクマの巣になってその道が街への導線になります。こうした、いくつもの要因が積み重なって、クマと人間の距離は徐々に離れ、クマの繁殖がクマの自然減・駆除数を上回っていると考えられます。従来奥山でひっそりと暮らしていたクマたちですが、奥山に増加したクマが収まることができなくなり、その生息域を徐々に広げてきたのではないでしょうか。
人里に出没したクマを駆除することは、クマの頭数削減に直接的に貢献するものですが、クマの出没そのものを防ぐ効果的な策とは言えません。クマが出没してしまったら、そこにはクマが出没する導線が形成されていることが示唆され、周辺の環境を変える必要があります。現在、里山には杉や檜が高密度に植林され、かつて美しかった景観が失われています。野生鳥獣にとっても高密度な針葉樹林は生息に適さないことが分かっており、食べ物も少ないことから、ただ人間に花粉症を引き起こさせる負の遺産であることは間違いないです。事業性は乏しいですが、針葉樹を伐採し、広葉樹を植林して森を再生させることで一昔前の景観が復活し、観光資源の再創出と野生鳥獣たちの住処を提供することが可能です。
我々は今一度、クマの住処である森についてその管理と現状の環境をよくよく考える必要があります。
これまでに私が読んだツキノワグマの知識を深めるための書籍
- ツキノワグマのすべて、小池伸介著、澤井俊彦写真提供、分一総合出版、2022年出版 ★おすすめ★
- ツキノワグマの生態学、信州大学山岳科学総合研究所、オフィスエム、2011年発行
- わたしのクマ研究、小池伸介著、さ・え・ら書房、2017年出版
- ある日、森の中でクマさんのウンコに出会ったら、小池伸介著、辰巳出版、2023年出版
- 人を襲うクマ、羽根田治著、山崎晃司解説、山と渓谷社、2021年出版
- 人狩り熊、米田一彦著、つり人社、2018年出版
- ツキノワグマ、宮崎学著、偕成社、2006年出版
- 「クマの畑」をつくりました、板垣悟著、地人書館、2005年出版
- ツキノワグマを追って、米田一彦著、小峰書店、1994年出版
- ツキノワグマ、山崎晃司著、東京大学出版会、2017年出版
- 滅びゆく森の王者ツキノワグマ、皮膚件哺乳動物調査研究会編著、岐阜新聞・岐阜放送、1993年発行
- 山でクマに会う方法、米田一彦著、山と渓谷社、2011年出版
- ツキノワグマのいる森へ、米田一彦著、丸善、1999年出版
- クマが樹に登ると、小池伸介著、東海大学出版会、2013年出版
- 写真集 秋田市にはクマがいる、加藤明見、無名舎出版、2018年出版
7DMarkII Canon EF100-400mm EF400mmf4 EF500mmF4LISIIUSM EOSR7 EOS RP FE200-600mm FEマウント HOKUTO ILCE-7RM3 ILCE-7RM5 ILCE-9 Instagram K-S2 PENTAX R5MarkII Sigma150-600mm SKYLUM SNS戦略 Sony TAMRON α7RIII オオワシ ツキノワグマ ネイチャー フィーチャー フォトコン プリント ミラーレス ミラーレス一眼 レビュー 一眼レフ 仁別 写真 写真現像 動物 望遠レンズ 海鷲 秋田 自然風景 超望遠レンズ 野生鳥獣 野鳥 風景